にがりが豆腐の歴史を変えた!豆腐マイスター協会理事長に聞く、知られざる豆腐の歴史秘話 #1

weeeat!編集部のレシピ開発担当、栄養士で豆腐マイスターの山崎が、豆腐の魅力を余すことなくお伝えするシリーズ。今回は、豆腐マイスター協会理事長の磯貝さんに豆腐の歴史について聞いてきました。一体日本ではいつ頃から豆腐は食べられていたのでしょうか?日本に伝わった経緯や製造方法の変化など、知られざる豆腐の歴史を紐解いていきます。
▼この連載の他の記事はこちら
豆腐マイスター協会理事長直伝!豆腐の旨味が倍増する美味しい食べ方&意外な油揚げアレンジ #2
" 作り手"こそ豆腐の魅力!美味しい豆腐を未来へ残すためにできること #3
中国だけじゃなかった!豆腐の3つの伝来ルート
―weeeat!編集部
先日は、豆腐マイスター講座でお世話になりました。
普段何気なく食べていた豆腐ですが、その歴史や製造方法、そして多様な調理法について学ぶことで、新しい視点を持つことができました! 豆腐作り体験も楽しかったです。
今日は、講座では聞けなかったさらに深いお話も伺えたらと思っています。
まずは、豆腐の歴史について教えてください!
―磯貝さん
こちらこそありがとうございました。
日本の豆腐の歴史を語る上で重要なのは、凝固剤です。凝固剤には、硫酸カルシウムとにがりの主に2種類あります。
まず、硫酸カルシウムは石灰を原料とし、豆腐にすっきりとした風味を与えます。一方、にがりは海水から抽出される塩化マグネシウムを主成分とする液体です。硫酸カルシウムよりも強い凝固力を持つため、大豆本来の旨味や甘味をぎゅっと閉じ込めた、濃厚な豆腐を作ることができます。
この2つの凝固剤が時代と共に主役の座を交代しながら、現在の豆腐の多様な味わいを生み出してきました。
―weeeat!編集部
豆腐マイスター講座で2つの凝固剤の豆腐を食べ比べしましたが、味わいがかなり違ってびっくりしました。
では早速、日本にはどのように伝わったか教えてください。
―磯貝さん
実は3つルートがあるんですよ。
1つ目は、奈良時代の遣唐使です。これは1番有力説ですね。
2つ目は、豊臣秀吉が朝鮮出兵の時に豆腐の技術者を高知県に連れて帰ったという説です。高知県の豆腐は硬さが特徴的で、朝鮮半島由来の製法ではないかと言われているんです。また、どんぐりの実を使った「かし豆腐」という豆腐があるのですが、これも朝鮮半島の豆腐と製法が似ています。
そして3つ目のルートは、沖縄を経由して伝わってきたという説です。台湾ルートで琉球王朝に伝わり、その後日本本土へ伝わったと考えられています。沖縄の島豆腐は、中国本土の豆腐よりも固く、また、にがり以外の凝固剤を使うこともあるなど、独自の進化を遂げています。
奈良時代の豆腐はにがりなしの木綿豆腐!?
―weeeat!編集部
中国、朝鮮半島、そして沖縄の3つのルート、それぞれに特徴があるのですね! 奈良時代に最初に伝わった豆腐はどんな豆腐だったのでしょうか?
―磯貝さん
奈良時代、日本にはまだにがりがありませんでした。そのため、豆腐を固めるには石灰から作る硫酸カルシウムという凝固剤が使われていました。現在の木綿豆腐のような形状をしていたと言われています。
当時の主流の製法は「生絞り」と呼ばれるもので、大豆を砕いてから絞って豆乳を作っていました。しかし、この方法では豆乳がどうしても薄くなってしまうため、しっかりと固めることができませんでした。そこで、固まった豆腐を型に入れて押し固め、水分を抜くことで、木綿豆腐のように仕上げていたと考えられています。
―weeeat!編集部
木綿豆腐と絹豆腐の違いに豆乳の濃度がありましたね。濃い豆乳を作るのが難しかった昔は、自然と木綿豆腐のような製法になったのですね。
にがりで豆腐が変わる! 江戸時代の豆腐革命
―磯貝さん
その後、豆腐の作り方がガラッと変わったのは江戸時代です。当時、豆腐は将軍が食べる高価な食べ物だったので、農民は特別な日にしか食べられませんでした。「豆腐禁止令」が出ていたこともあるんですよ。
―weeeat!編集部
豆腐禁止令ですか!?
―磯貝さん
驚きですよね。でも、あるキッカケで豆腐が大衆的な食べ物になっていきます。それは「塩田」です。塩田での塩作りが始まり、副産物のにがりが手に入るようになったことで、豆腐作りは大きく進歩したんですよ。
―weeeat!編集部
にがりの登場が、豆腐の歴史における大きな転換点だったのですね。
―磯貝さん
まさにその通りです。江戸時代後期になると、豆腐は徐々に庶民にも手が届くようになり、色んな豆腐料理が開発されていきました。『豆腐百珍』のような料理本が出版され、人々は多様な豆腐料理を考案し、楽しむようになったのです。
厚揚げや油揚げといった豆腐の加工品も、この時代に広まりました。
―weeeat!編集部
『豆腐百珍』を見ると、当時の豆腐料理のバリエーションがこんなにもあったなんて驚きですね!

「煮てから絞る」新製法でついに絹豆腐が誕生
―磯貝さん
そして、絹豆腐もちょうどこの頃に誕生しました。一部の豆腐屋さんが濃い豆乳を作る技術を開発し、絹豆腐を作ったのが始まりと言われています。「笹乃雪」という豆腐屋さんがその先駆けとして有名です。
彼らは、「煮てから絞る」という画期的な製法を編み出したと言われています。この方法によって濃い豆乳を作ることが可能になります。すると、木綿豆腐のように水を切らずに豆腐を作ることができるようになりました。こうして、絹豆腐特有の滑らかでぷるん食感が誕生したのです。
―weeeat!編集部
絹豆腐は日本で生まれたのですね! 新しい製法が生まれたことで、一気に豆腐が普及していったのでしょうか?
江戸から明治時代にかけて豆腐屋が急増
―磯貝さん
そうです。江戸時代から明治時代にかけて、豆腐屋さんはどんどん増えていきました。当時、豆腐は買うものではなく、家庭で作るものだったんですよ。農業が盛んになり、各家庭で大豆から豆腐を作っていました。
豆腐作りは、どの家庭でも行われていましたが、その腕前には差がありました。そこで、上手に豆腐を作れる人は、近所の人から「大豆はあるから、豆腐を作ってくれないか」と頼まれることが増えていきました。これが、豆腐屋という職業の始まりだったそうです。
―weeeat!編集部
当時は木綿豆腐と絹豆腐、どちらが主流だったのでしょうか?
―磯貝さん
絹豆腐は京都などの一部の豆腐屋さんで作られる特別なものだったので、全国的には木綿豆腐が主流でした。なので、「うちは江戸時代後期から豆腐を作っています」という老舗の豆腐屋さんも、作っていたのは木綿豆腐が多かったはずです。
戦争の影響でにがりが消えた
―weeeat!編集部
そうなんですね。凝固剤はにがりが主流だったのでしょうか?
―磯貝さん
昭和の前半まではそうでした。それが戦争をキッカケに様変わりしてしまいます。
第二次世界大戦中、にがりは戦闘機などのジュラルミンを作るために必要だったため、軍需物資として統制されるようになったのです。そのため、豆腐作りには使えなくなってしましました。そうして、再び硫酸カルシウムを使う豆腐作りへと戻っていったのです。
―weeeat!編集部
戦争が関係していたとは、驚きです!
―磯貝さん
このような背景から、にがりを使った豆腐作りが一度途絶えてしまいます。その後、平成までは硫酸カルシウムやグルコノデルタラクトンなど別の凝固剤の時代が続きます。
戦後、豆腐屋の数はコンビニエンスストア並みに
―磯貝さん
戦後になると、仕事にあぶれた人たちが豆腐屋さんを始めるケースが増えました。昭和25年創業の豆腐屋が多いのは、そのためです。大豆は配給制で、豆腐を作るには全豆連(全国豆腐製造協同組合連合会)に加入して配給を受ける必要がありました。
―weeeat!編集部
ということは、豆腐作りは誰でも始めることができたのでしょうか?
―磯貝さん
そうですね。当時、機械ではなく石臼と布を使い、手作業で豆腐を作っていました。設備投資がほとんど必要ありません。また、硫酸カルシウムは凝固反応が遅いので、ある程度作りやすかったんです。豆腐を作れば、それなりに生活することができ、子どもを大学に行かせることもできました。
戦後間もない肉や魚が不足していた時代、豆腐は貴重なタンパク源でした。「作れば売れる」時代だったんです。昭和35年頃がピークで、豆腐屋さんの数はコンビニエンスストア並みにあったと言われています。
―weeeat!編集部
なるほど。豆腐屋さんがたくさん生まれたのも頷けます。
作れば売れる時代が終わり競争激化
―磯貝さん
しかし、スーパーマーケットが登場すると、豆腐屋さんは作った豆腐を卸すようになり、競争が始まりました。商品を差別化しなければ売れなくなり、そこで国産大豆やにがりを使った豆腐作りに注目が集まり始めました。
―weeeat!編集部
ここでにがりが復活するのか! 「作れば売れる」時代から「品質で勝負する」時代へと変わっていったんですね。
―磯貝さん
その通りです。国産大豆を使うと、コストは倍以上かかります。それでも、より美味しい豆腐を作るために、豆腐屋さんは研究を重ねました。そして昭和60年頃には、国産大豆とにがりを使った豆腐が登場し始めました。
今では、全国で販売されている豆腐の約9割がにがりを使った豆腐ですね。とはいえ、京都では湯豆腐など、伝統的な料理には硫酸カルシウムを使った豆腐が使われています。なぜなら、出汁の風味や料理の味を活かすためには、にがりの豆腐よりもすっきりとした味わいの硫酸カルシウム豆腐の方が合うからです。
―weeeat!編集部
今、当たり前のように国産大豆とにがりを使った豆腐を食べられるのも、豆腐屋さんの努力のおかげなんですね!
確かに、硫酸カルシウムのお豆腐はこの辺のスーパーだとあまり見かけませんね。
―磯貝さん
そうですね。京都でも、街の豆腐屋さんでないと手に入らないことが多いです。しかも、成分表示に「硫酸カルシウム」と明記されていることは稀で、「昔ながらの製法」などと書かれているので少し難しいかもしれません。
豆腐を日本からアメリカへ!森永の挑戦
―weeeat!編集部
国内の豆腐の歴史がよーく分かりました!
ここで海外の豆腐についても教えてください。豆腐マイスター講座の聞いた、森永のお話が印象に残っています。豆腐をアメリカに広げようとしたんですよね?
―磯貝さん
『豆腐バカ 世界に挑む』の話ですね! もともとアメリカでは大豆を家畜の餌や搾油用として生産していましたが、食用としては考えられていませんでした。「大豆は人間の食べ物ではない」という認識が一般的だったのです。
そんな中、1980年代に森永が豆腐をアメリカに持ち込み、普及活動を始めました。アメリカには中華系の人たちを中心に豆腐を食べる文化が既にあったので、その日本食に馴染みのある人たちに向けて豆腐を売り込もうとしました。
しかし、当初は思うように売れず、売れ残りが山積みになることもありました。泥棒に入られても、豆腐だけは盗まれずに残っていた、なんていう話もあるくらいです。
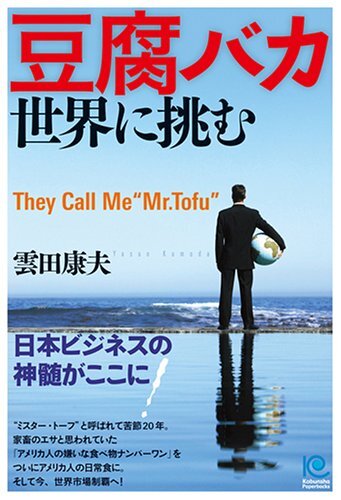
普及のキッカケはヒラリー・クリントン
―weeeat!編集部
なかなか普及しなかった豆腐が、どのようにしてアメリカで受け入れられるようになったのでしょうか?
―磯貝さん
転機が訪れたのは、アメリカで健康ブームが起き始めた頃です。肥満が社会問題化し、ヘルシーな食生活への関心が高まる中で、豆腐が注目され始めました。しかし、今度は「どうやって食べるんだ?」という新たな壁にぶつかりました。
それでも、森永は諦めずに10年間も普及活動を続けました。そしてついに、ヒラリー・クリントン氏が「豆腐はヘルシーらしい」という情報に注目します。豆腐メーカーがクリントン氏に豆腐を送り、試食してもらったところ、「食べた方がいいわよ」と発信してくれて、豆腐は一気に広まりました。
―weeeat!編集部
ヒラリー・クリントン氏の発言で一気に広がったのですね。すごい! どんな食べ方が受け入れられたのでしょうか?
―磯貝さん
スムージーに入れたり、ドレッシングの代わりにしたり、豆腐ステーキとして肉料理の代わりにしたりと、色んな食べ方で受け入れられました。特に、豆腐ステーキは肉よりもヘルシーな代替品として人気だったそうですよ。
―weeeat!編集部
豆腐は形を変えることで、様々な料理に姿を変えるんですね。可能性は無限大!
―weeeat!編集部
今回は、豆腐の歴史について詳しくお伺いしました。日本で生まれた豆腐が、時代とともに凝固剤が入れ替わり様々な形で進化してきたことに感動しました。
―磯貝さん
豆腐の歴史は本当に奥深いですよね。ぜひ、色んな凝固剤の豆腐を食べ比べてみてください。
―weeeat!編集部
豆腐の食べ比べ、コラムの企画でやってみたいです。次回は、豆腐の美味しい食べ方について教えてください。
プロフィール
日本豆腐マイスター協会理事長 磯貝剛成さん
ウェブサイト:https://mytofu.jp/
Instagram:https://www.instagram.com/tofumeister/
▼この連載の他の記事はこちら
豆腐マイスター協会理事長直伝!豆腐の旨味が倍増する美味しい食べ方&意外な油揚げアレンジ #2
" 作り手"こそ豆腐の魅力!美味しい豆腐を未来へ残すためにできること #3



